私ももともと生物系の研究をしていたので、半導体や強誘電体については全くの未経験でした。
入社当初は「大丈夫かな」と不安でしたが、入社直後に研修があり、メモリ全般の基礎や強誘電体の仕組みを学ぶ機会がありました。
とはいえ、研修だけで全てを理解するのは難しいので、実務を通じて日々学びながら、分からないことがあればベテランの先輩に質問しながら覚えていきましたね。

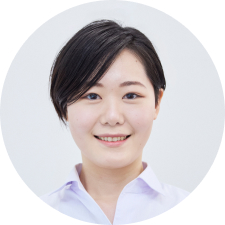
N.S
私ももともと生物系の研究をしていたので、半導体や強誘電体については全くの未経験でした。
入社当初は「大丈夫かな」と不安でしたが、入社直後に研修があり、メモリ全般の基礎や強誘電体の仕組みを学ぶ機会がありました。
とはいえ、研修だけで全てを理解するのは難しいので、実務を通じて日々学びながら、分からないことがあればベテランの先輩に質問しながら覚えていきましたね。

A.I
確かに研修はありますが、知識ゼロの状態だと、研修だけでは完全に理解するのは難しいですよね。でも、業務を任せてもらう中で、少しずつ知識を吸収しながら成長していく感じでした。やっぱり経験を積むことで自然と身についていくのかなと。

M.Y
私は大学では半導体の成膜関係を研究していましたが、入社後は加工(エッチング)に配属になりました。これまで扱ったことがない分野だったので、「どの学科から来てもスタートは一緒なんだな」と実感しましたね。
知識がある程度あっても、社内で使われる専門用語や、大学の研究とは異なる「量産」という視点での業務には戸惑いました。でも、その違いを学びながら仕事を進めることで、より深く理解できるようになりました。


H.M
皆さん、バックグラウンドが違う中で、それぞれ成長されているんですね。では、大学時代の経験が仕事に活かされたと感じることはありますか? 研究内容だけでなく、サークル活動やアルバイトなど、何でも構いません。
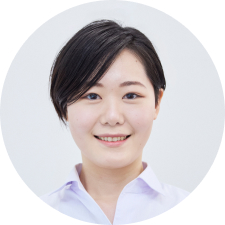
N.S
飲み会でのコミュニケーションは役立ちましたね(笑)。会津若松は日本酒が美味しいので、お酒が好きな方と話す機会も多いんです。大学時代にその経験があったのは良かったなと。

M.Y
私はあまり飲みませんが、大学時代の経験で役立ったのは、オープンキャンパスでの研究室紹介や、学祭の実行委員ですね。人前で話したり、プレゼンをしたりする機会が多かったので、それが今の仕事で意見を伝える場面で活きていると思います。

A.I
私は大学院時代、研究で「とにかく考えて仮説を立てる」ことをよくやっていました。正解が分からなくても、まずは考察を組み立てて、担当教員に意見をぶつけてみる。その経験が、今の業務でも「とりあえず考えてみる」という姿勢につながっていると思います。

H.M
なるほど。正しいか分からなくても、まずは自分で考えて、意見を持つことが大事ですね。
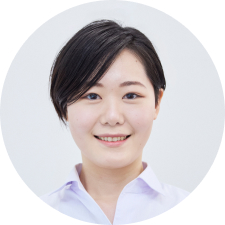
N.S
OJTは担当の先輩がついてくださり進んでいくのですが、一年修了時に、新人研修発表会を行う文化があることにびっくりしました。ただ、成果報告を作るにあたり、OJTの先輩だけでなく他のベテラン社員にもアドバイスをもらい、成長につながりました。

A.I
確かに、新人研修発表会は全社で役員も交えてやると思っていなかったのでいい緊張感をもって、資料作りや発表ができました。

M.Y
私の新人研修発表会の時は、オンラインで開催だったのでリアルほどではありませんでしたが、資料作りで何度もフィードバックをもらい作り直しました。そのときに思ったのが、誰に向けて資料を作るかという点です。部内ならより詳しい内容を、社内なら他部門にも伝わりやすく概要をまとめた資料を作ることを学びました。
またOJTは最初の1か月で全体像を学び、実際の装置をいじるなど詳しいことを学びます。私のOJT担当先輩は、より深い知識を教えてくださる方だったので装置の構造など深いことまで教えて頂き、とても良かったと感じています。


H.M
今の研修では、研修用のデータを使って発表されていますが、私の時代にはもう少し規模の大きい研修が行われていました。
当時は社員の数も多く、発表のために「テストサンプル」を実際に作成し、その結果を含めて発表するという内容でした。ウェハーを組み立て、プロセスを通し、得られたデータを元に成果を発表する、実践的な研修でしたね。

M.Y
グループ単位で行っていたんのですか?

H.M
はい。4人ほどのグループを作り、10グループくらいで取り組んでいました。1年目から一通りの製品設計プロセスをトレースできる内容だったので、とても良い経験になりました。
しかも、テストサンプルなので、仮に失敗してもお客様に迷惑がかからない。そのため、思い切って挑戦できる研修だったと思います。
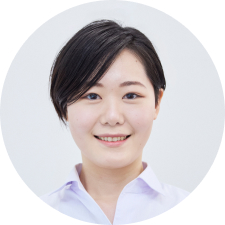
N.S
それは、面白そうですね!

A.I
テーマ自体は、配属された段階で決めてあって、それに沿って準備・発表を行います。

H.M
ただ、与えられたテーマの中で切り口は自分で考えて行います。1年目の後半から、みんな頭をひねらせはじめ、最後の一ヶ月で資料を追い込んで作ってドキドキして発表するという感じでした。みなさんとてもよい発表でした。

H.M
とても難しいのですが、「教えすぎない」ことを意識しています。ベテランと若手では経験の差が大きいので、つい手取り足取り教えたくなるのですが、それでは自分で考える力が身につかない。
かといって、何も教えないと業務が進まないので、その匙加減が難しいですね。いかにバランスよく指導するかを、常に意識しています。

A.I
実は、H.Mさんに直接指導していただいたことがあるんですが、そんなことを考えながら教えてくださっていたんですね。今知りました。(笑)
全部教わっていたのかもしれませんね。(笑)

M.Y
私は「ヒントをもらって、あとは自分で考える」スタイルでした。時には意見が食い違うこともあり、1年目から担当の方と結構言い争いをしていました。(笑)

H.M
やる気があっていいですね!うちの会社にとってプラスになります!