- ホーム
- RAMXEEDを知る
- 社員インタビュー
- R.S(設計エンジニア)
INTERVIEW 社員インタビュー
難しい課題を乗り越えた時の、 大きな達成感。


R.S設計
エンジニア
| 入社年 | 2019年 |
|---|---|
| 出身学部 | 工学部 有機材料システム |
| 勤務地 | 新横浜 |
- お仕事の内容をお聞かせください。
-
弊社で設計・開発しているメモリには、お客様専用の「カスタム品」と、広く一般に使われる「汎用品」があります。私はその中でも汎用品の設計開発を担当するチームに所属しています。
具体的には、メモリのデータを読み書きする「マクロ」と呼ばれる部分の論理設計を担当しています。論理設計とは、メモリの仕様をハードウェア記述言語でプログラムし、設計を行う仕事です。実際の業務では、記述したプログラムの動作をシミュレーションで検証し、正常に動作するかを確認する作業を行っています。
シミュレーションである程度の動作は確認できますが、最終的には波形を人の目でチェックする必要があり、細かい確認作業が求められます。非常に大変な仕事ですが、メモリの正しい動作を保証するために重要な役割を担っています。
仕様を間違えて記述したり、検証が不十分だったりすると、製品が動かなくなってしまったり、不具合が発生したりする可能性があります。そのため、不具合を減らすためにも、仕様や各回路の動作をチームですり合わせることが重要です。また、実際に製品化された際に問題なく動作するかを確認するため、検証方法を日々アップデートしていく作業も重要です。
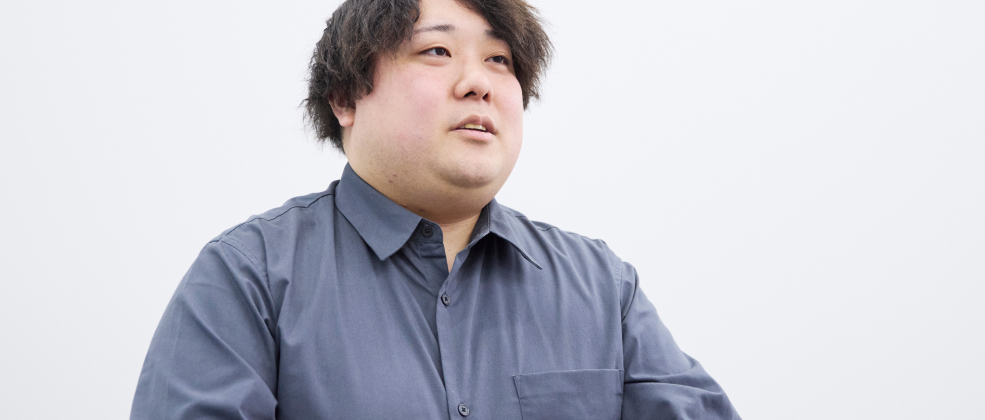
- 大学では何を専攻されていましたか?入社後、戸惑いはありましたか?
-
私は大学時代、有機半導体を研究していました。弊社では有機半導体は扱っていませんが、半導体の動作に関する基本的な知識があったため、設計業務に入る際のハードルは比較的低かったと感じています。
しかし、メモリや設計に関する知識はほとんどなかったため、専門用語や社内用語を覚えるのに苦労しました。最初は会議で何を話しているのかまったく分からず、聞き取ることさえ難しい状況でした。会議中に分からなかった部分については、録画を見直して、振り返りながら理解を深めていました。
ただ、社内では定期的に勉強会が開かれており、分からないことを学ぶ機会も充実しています。勉強会では、事前に先輩社員に「この単語が分からない」「設計のこの部分が分からない」などの質問をリストアップし、インプットの機会を設けてもらうことができます。また、一度学んだことを自分なりに整理し、他の若手社員にも分かりやすく共有するアウトプット型の勉強会もあります。こうした取り組みを通じて、設計や業務に必要な知識を身につけていくのが、私の部署のスタイルです。
- 入社してから成長したことや、スキルアップされたことを教えてください。
-

入社後は、まずトランジスタレベルの設計から学び、1年目は主にマクロ開発グループで設計の基本を教わり、最終的には既存のマクロの修正する研修を通じ、設計時に必要な検証について学びました。2年目からは先輩社員についてもらい、OJTとしてハードウェア記述言語を学びながら、メモリのコアとなるマクロのライブラリの作成や検証を経験しました。
最初は論理を記述する作業が中心でしたが、業務に慣れてきた段階でマクロの回路設計にも携わるようになりました。回路設計では、単に論理を考えるだけでなく、トランジスタや抵抗、コンデンサ、FeRAMの電気的な特性を考慮しながら設計を行う必要があります。シミュレーションを通じて結果を確認しながら設計していくため、幅広い知識が求められる難しい業務ですが、簡単な設計から少しずつ経験を積み、理解を深めていきました。
-
その後、製品担当を任されるようになりました。製品担当の仕事では、設計部門だけでなく、半導体の前工程(プロセス)、パッケージ化してメモリの形にする工程など、製品化に関わるすべての調整を行い、課題を解決していく役割を担います。この業務では特に幅広い知識が必要となるため、先輩社員のサポートを受けながら日々学びつつ、少しずつ対応できる業務の幅を広げています。
- お仕事のやりがいを教えてください。
-
仕事をしていてやりがいを感じたのは、初めてライブラリのマクロの論理開発を1人で担当したときです。それまでは先輩に頼りながら作業していましたが、このときは初めて完全に自分1人で進めることになり、大きな責任を感じました。
開発を進める際に、設計ツールが変更になり、これまでの技術ではエラーが発生するようになってしまいました。さらにメモリの容量が異なる2つの製品を開発する必要があり、論理は共通でも、それぞれに合わせた調整が求められました。2つのスケジュールを管理しながら、新しいツールに適応する必要があり、非常に大変な業務でした。
作業を進める中で不具合が発生し、どうしても分からない部分は先輩に助けていただきながら対応しましたが、最終的には納期通りに開発を完了し、次の工程へと引き継ぐことができました。
難しい課題を1人で乗り越えることができたことで、大きな達成感を得られましたし、「会社に貢献できている」という実感を強く持つことができました。とても良い経験になったと思います。
- 職場の雰囲気はいかがですか?どんな社員の方が多いですか?
-
出社時は、フリーアドレス制が導入されているため、出社時も先輩や仲のいい同僚の隣に座って作業でき、かしこまらずに自由に働ける環境です。
先輩社員は気軽に質問しても優しく答えてくれる方が多く、新横浜の後輩や同期もまじめで落ち着いた雰囲気の人が多いため、働きやすい職場だと感じています。
出社時には、先輩や後輩とランチに行ったりもします。
- プライベートとワークライフバランスについて、教えてください。
-
平日は週3回の在宅勤務があり、フレックス制度も活用できるため、プライベートと仕事のバランスを取りやすい環境です。例えば、夕飯をゆっくり作ったり、趣味の海外サッカー観戦のために朝早く起きる生活リズムを調整しています。試合を見る日は在宅勤務にすることで、業務に支障が出ないよう睡眠時間を調整しながら無理なく観戦できています。
また、休日は大学時代の友人とゲームをしたり、サッカー観戦や古着屋巡りを楽しんでいます。
在宅勤務中のコミュニケーションは基本的にチャットや、記録を残すためにメールでのやりとりが中心ですが、設計の仕事では文章に起こすのが大変な場面も多いため、オンラインで画面共有をしながら打ち合わせをすることがよくあります。
お互いが在宅同士のときも、「ここが分からないのですが、なぜこうなっているのですか?」といった具体的な質問をしながら、スムーズにコミュニケーションを取ることができる環境になっています。
- これから挑戦されたいお仕事はありますか?
-
これまでは、メモリの読み書きを担う「マクロ」と呼ばれる部分の設計を主に担当していました。しかし今は、製品担当として製品に携わる業務の取りまとめをしたり、メモリ全体を論理検証する業務にも携わっています。
今後は、マクロ設計だけでなく、製品全体を見渡しながら設計を進め、論理設計と製品開発の両方で成果を出せる設計者を目指したいと考えています。

1日のスケジュール例
(フレックス勤務)
- 8:45
- 出社、メール確認
- 9:15
- 実験
- 11:00
- 打ち合わせ
- 11:45
- 昼食
- 12:45
- 昼礼
- 13:00
- データ整理
- 15:00
- 打ち合わせ
- 17:00
- メール確認
- 17:30
- 退社
